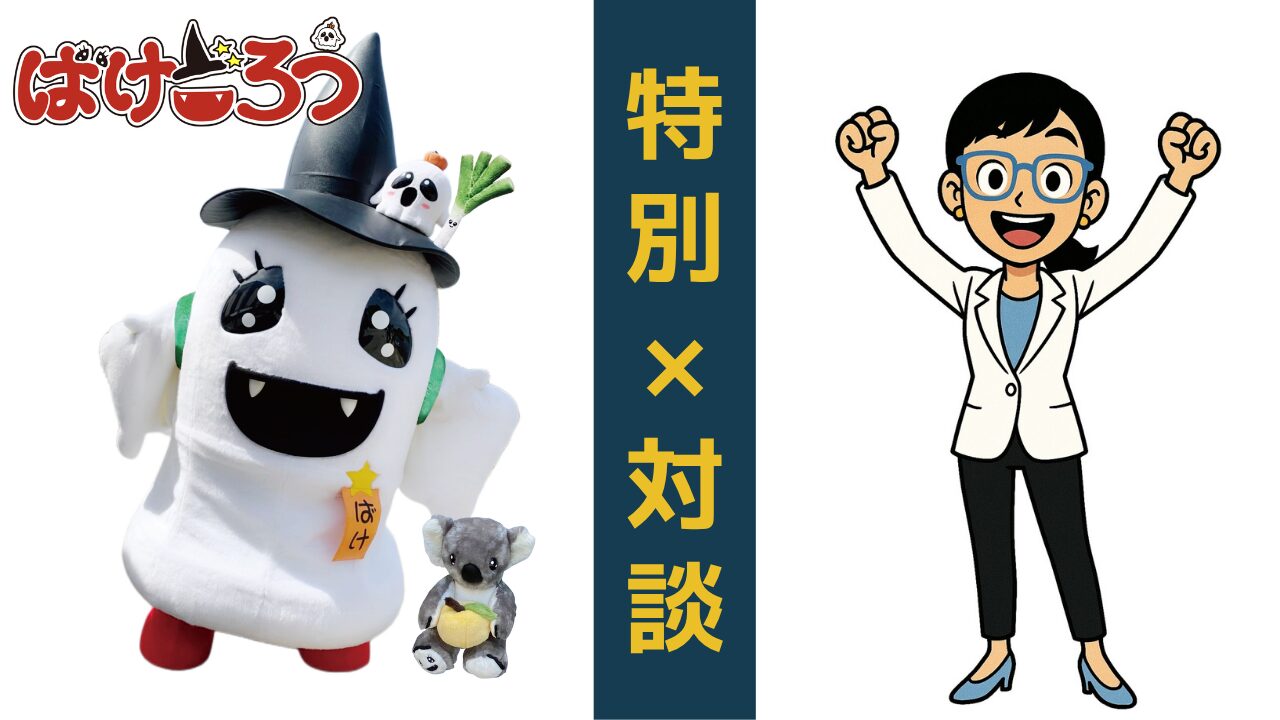【2025年人流データ分析】松戸市4大拠点(松戸・新松戸・八柱・東松戸)の都市特性と東松戸の住みやすさと将来性

市内4拠点の特性をデータで読み解く
本記事では、千葉県松戸市内の4つの主要拠点(松戸、新松戸、八柱、東松戸)を、人流ビッグデータなどの客観的なデータに基づいて比較分析します。
松戸エリア
市の商業・行政の中心地。来街者と勤務者が多く、市の経済活動の心臓部としての役割を担っています。
2,563万人
月平均滞在人口
63%
居住者比率
23%
来街者比率
6%
外国人 初回訪問比率
滞在者属性
年代別構成
訪日外国人:訪日回数
このエリアを訪れる外国人の訪日経験を比較します。リピーターが多いか、初めての訪問者が多いかによって、エリアの国際的な役割が見えてきます。
訪日外国人:滞在時間帯
外国人の滞在がどの時間帯に集中しているかを示します。特に「朝」や「深夜」の多さは、空港利用の前泊・後泊需要を示唆します。
エリアの特性
強み (メリット)
- 最高の利便性、商業施設が充実
- 交通のハブでアクセス良好
- 全国トップクラスの子育て支援
弱み (デメリット)
- 駅西口の治安への懸念
- 雑然とした雰囲気、交通混雑
- 居住環境としては好みが分かれる
多面的な顔を持つ街、松戸市

千葉県北西部に位置する松戸市。都心へのアクセスの良さからベッドタウンとして発展してきたこの街は、近年、多様な魅力を持つ都市へと進化を遂げています。
松戸市の都市戦略の特徴は、一つの中心地に機能を集中させるのではなく、市内に点在する複数の拠点がそれぞれ独自の役割を担う「多極ネットワーク型」のまちづくりを進めている点にあります。
データが語る松戸市:個性豊かな4つの拠点
これまで漠然としたイメージで語られがちだった各地域の特性を、客観的なデータで見ていきましょう。今回の分析の根拠となるのは、KDDIの位置情報ビッグデータを活用した詳細な人流データです。これにより、各拠点に「誰が」「どのような目的で」滞在しているのかが、具体的な数値で明らかになります。
表:松戸市4大拠点の人流プロファイル(月平均)
| 項目 | 松戸駅周辺 | 新松戸駅周辺 | 八柱・新八柱駅周辺 | 東松戸駅周辺 |
|---|---|---|---|---|
| 滞在人口総数 | 約2,563万人 | 約2,732万人 | 約957万人 | 約693万人 |
| 滞在者属性 | 居住者: 64% 勤務者: 15% 来街者: 21% | 居住者: 82% 勤務者: 8% 来街者: 10% | 居住者: 76% 勤務者: 8% 来街者: 16% | 居住者: 70% 勤務者: 11% 来街者: 19% |
| 年代別構成(特徴) | 30代-40代が多い (計38%) | 20代・70歳以上が多い (計44%) | 70歳以上が多い (25%) | 30代-40代が突出 (計45%) |
出典:松戸市公開資料(2024年度データ)を基に作成
この表から、各拠点の明確な役割分担が見て取れます。
松戸駅周辺:市の活気を牽引する「中心業務地区」
「来街者(買い物客など)」と「勤務者」の割合が圧倒的に高く、名実ともに松戸市の商業・行政の中心地です。駅直結の「アトレ松戸」や「プラーレ松戸」、「KITE MITE MATSUDO」といった大規模商業施設が集積し、常に多くの人で賑わっています。利便性が非常に高い一方で、住民からは混雑や雑然とした雰囲気を指摘する声も聞かれます。
新松戸駅周辺:交通と学術が交わる「大規模居住・結節点」
滞在人口の総数が4拠点で最も多いものの、その8割以上が居住者で占められています。JR武蔵野線と常磐線が交差する交通の要衝であり、駅周辺には流通経済大学のキャンパスも存在します。そのため、20代の若者と、古くから住む高齢者層が共存する成熟した住宅地としての性格が強いエリアです。
八柱・新八柱駅周辺:緑と暮らしが調和する「レクリエーション・居住拠点」
滞在人口の約4分の3が居住者であり、穏やかな住宅地が広がっています。このエリアを特徴づけるのは、広大な「21世紀の森と広場」の存在です。豊かな自然と文化施設(松戸市立博物館)が融合し、地域住民の憩いの場であると同時に、市外からも人々を惹きつけるレクリエーション拠点となっています。
そして、本記事の主役である東松戸は、これらの拠点とは全く異なる発展の軌跡を辿っています。
東松戸の「今」を徹底解剖:計画された子育て世代の街

東松戸の発展は、自然発生的なものではなく、市の明確なビジョンに基づいた計画的なまちづくりの産物です。かつて病院建設予定地だった広大な土地は、「東松戸まちづくり用地活用事業」によって、新しいコミュニティの中核へと生まれ変わりました。
その象徴が、2021年にオープンした複合施設「ひがまつテラス」です。
図書館、市役所の支所、そして子どもたちのための青少年プラザが一体となったこの施設は、まさに東松戸が目指す「コミュニティと学びの交流拠点」というコンセプトを体現しています。
データが証明する「子育て世代の集積」
東松戸の最大の特徴は、その人口構成にあります。
先の表で示した通り、滞在人口における30代(19%)と40代(26%)の比率の合計は45%に達し、他の3拠点を大きく引き離しています。
これは、松戸市が推進する「三世代同居等住宅支援制度」や積極的な保育施設の整備といった子育て支援策が功を奏し、狙い通り若いファミリー層を惹きつけていることの何よりの証拠と言えるでしょう。
住民の声から見る「東松戸の住みやすさ」のリアル

データは街の骨格を示しますが、その住み心地は実際に暮らす人々の声に表れます。住民レビューを分析すると、東松戸の生活環境における明確なメリットとデメリットが浮かび上がります。
強み(メリット):静かで安全、新しい街並み
住民から一貫して高く評価されているのは、「静か」「穏やか」「安全」といった住環境の質です。
- 整然とした街並み:近年の区画整理により、道路は広く歩道も整備され、電線地中化も進んでいます。新しく美しい街並みは、ベビーカーを押して歩くにも安心です。
- 豊かな自然:駅周辺にも「東松戸中央公園」などの公園が点在し、少し歩けば梨園が広がるなど、都市の利便性と自然の潤いが両立しています。
- 強いコミュニティ:新しい住民が多いため、住民間のコミュニティ意識が生まれやすく、特に子育て世代にとっては心強い環境です。
これらの要素が組み合わさり、東松戸は「子育てに最適な環境」として多くの家族に選ばれているのです。
弱み(デメリット):商業施設の不足と交通費
一方で、住民が不便さを感じる点も明確です。
- 商業施設の選択肢の少なさ:駅前にスーパーマーケット「ベルク」やドラッグストアなどがあり、日常の買い物に不便はありません。しかし、衣料品や雑貨、あるいは多様な飲食店を求める場合、松戸駅周辺や他のエリアへ足を運ぶ必要があります。
- 北総線の運賃:都心へのアクセスは、北総線と都営浅草線の直通運転により非常に便利です。しかし、その運賃が他の路線に比べて割高であることは、住民にとって長年の課題であり、大きな負担となっています。
世界とつながるゲートウェイ?東松戸の意外なポテンシャル

東松戸には、もう一つ注目すべき顔があります。それは、国際的な「空港ゲートウェイ」としての役割です。
訪日外国人に関する人流データを分析すると、驚くべき事実が判明しました。
2024年7月のデータによると、松戸駅周辺を訪れる訪日外国人の94%が日本に2回以上来ている「リピーター」であるのに対し、東松戸駅周辺では「初回訪問」の旅行者が58%と過半数を占めています。
さらに、滞在時間帯を見ると、他の拠点では「昼」に集中するのに対し、東松戸では「朝」や「深夜」の滞在も多く見られます。
これらのデータが示すのは、東松戸が成田空港と羽田空港の両方に乗り換えなしでアクセスできる北総線・成田スカイアクセス線の利便性から、フライト前後の宿泊・一時滞在拠点、すなわち「トランジット拠点」として利用されている実態です。
これは、東松戸が単なるベッドタウンに留まらず、日本の玄関口として国際的な役割を担うポテンシャルを秘めていることを示しています。
まとめ:市内4拠点の特性をデータで読み解いてみて見えてきたこと
今回のデータ分析を通じて、松戸市が推進する「多極ネットワーク型」の都市構造が、具体的な数値となって浮かび上がってきました。市内の4つの拠点は、それぞれが競合するのではなく、明確な役割分担によって市全体の魅力を高めていることがわかります。
- 松戸駅周辺は、圧倒的な来街者数と商業施設が集積する、議論の余地なき「市のエンジン」。
- 新松戸駅周辺は、最大の居住人口と交通の利便性が融合した「暮らしと移動のハブ」。
- 八柱・新八柱駅周辺は、豊かな自然と穏やかな住環境が調和した「憩いとウェルビーイングの拠点」。
- 東松戸は、市のビジョンに基づき、「子育て世代」を主役として創出された新しいコミュニティです。
本記事で示した客観的なデータが、ご自身のライフスタイルに合った街選びをされる上で、そして東松戸という街のリアルな姿を理解する上での一助となれば幸いです。